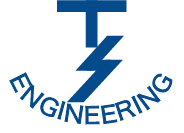電気設備は、現代社会におけるあらゆる建物・施設に欠かすことのできない基盤インフラであり、その役割は大きく二つに分けられる。ひとつは、電力を「生み出し」「送る」ための電力会社側の設備。もうひとつは、その電力を「受け取り」「使用する」ための需要家側の設備、すなわち構内電気設備となる。
電力会社が保有・管理する設備には、発電所などの「発電設備」、電気を遠距離へと運ぶ「送電設備」、電圧を適正に変換する「変電設備」、そして最終的に各需要家へと配る「配電設備」が含まれる。これらの設備群が連携することで、発電所で生まれた電力は安定した状態で都市部や地方、工場、オフィスビル、一般家庭などへ届けられている。このプロセスを経て届けられた電気を、実際に活用するための設備が「構内電気設備」である。
具体的には、受変電設備、分電盤、幹線・配線設備、照明器具、電源コンセント、空調機器、昇降機、情報通信関連設備、そして非常用電源や火災報知設備などの防災関連設備まで、多岐にわたる装置やシステムが含まれる。これらは単に電力を供給するだけでなく、施設の機能性、居住性、安全性を高める重要な役割を担っている。
構内電気設備は、建築物の用途や規模、使用環境に応じて設計・施工される必要があり、高度な専門知識と経験が求められる分野。また、近年ではスマート化・省エネ化が進み、エネルギーマネジメントシステム(BEMS)やIoT対応設備の導入も加速しているため、電力の最適利用や環境負荷の軽減、ランニングコストの削減が実現されており、電気設備の設計・構築には、今まで以上に高い技術力と柔軟な対応力が必要となる。
私たちの生活や産業活動は、こうした電気設備によって見えないところで支えられており、照明が灯る、機械が動く、空調が快適に保たれる。その“当たり前”は、すべてこの設備が正常に機能していることによって成り立っており、 今後も電気設備は、省エネルギー性や再生可能エネルギーとの連携、防災・減災の観点など、さらに多様で高度な機能を求められていくだろう。そのためにも、時代のニーズを的確に捉え、安全性・信頼性・持続可能性を重要し施工を行う。