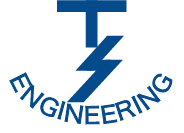電灯設備とは、主に単相100Vまたは200Vの電圧を使用する設備の総称であり、その中心となるのが照明設備。オフィスビル、商業施設、工場、住宅など、あらゆる建築物内において、空間の機能性と快適性を支える不可欠な設備のひとつ。
照明設備の中には、天井照明、壁面照明、間接照明などの各種照明器具が含まれるほか、弱電機器(パソコン、AV機器、情報端末など)を使用するためのコンセント設備も「電灯分電盤」からの配線として分類される。これにより、照明だけでなく、一般的な家庭用・業務用電源機器の電力供給も担っているのが電灯設備である。
照明設計の基本要素
照明設備の設計においては、単に部屋を明るくするだけでなく、「快適な視環境を構築する」という目的に基づき、以下のような複数の指標をバランス良く考慮する必要がある。
1. 照度(Illuminance)
照度とは、光が照らす面の明るさを数値化したもので、単位はルクス(lx)で表される。作業内容や用途に応じて適切な照度を確保することが求められる。たとえば、オフィスのデスク上では500lx前後が望ましく、展示施設や手術室などではさらに高照度が必要とされる。
2. グレア(Glare)
グレアとは「まぶしさ」の度合いを示す指標であり、照明設計において最も人間の快適性に影響を与える要素のひとつ。光源の輝度(cd:カンデラ)、光源の大きさ、視線との角度、距離などがグレアに影響する。国際的にはUGR(Unified Glare Rating:統一グレア評価値)により評価され、数値が低いほど不快感が少ない。照明計画では、使用空間におけるグレア基準値を超えないよう厳密な配慮が求められる。
3. 演色性(Color Rendering)
演色性とは、光源が物体の色をどれだけ自然に、正確に見せられるかを示す性能。太陽光を基準(演色評価数Ra=100)とし、演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近い見え方。特に、医療施設、美術館、小売店舗などでは高い演色性が必要とされ、照明器具の選定にも慎重な検討が必要。
これらの要素に加え、輝度分布、色温度、省エネ性能、人感センサーの有無など、多様な観点から照明計画は立案される。現代の照明計画では、単なる物理的な明るさの確保だけでなく、人間工学や心理的快適性も踏まえた「心理物理量」の観点が不可欠である。
照明器具の選定と空間演出
照明器具は、電気設備の中でも最も視認性が高く、空間の印象を大きく左右する重要な要素です。器具選定にあたっては、用途や設置環境に応じた明るさの確保だけでなく、光の広がり方、陰影の演出、デザイン性、配光特性(直接照明/間接照明など)、器具の効率や寿命も考慮される。 近年では、LED照明が主流となり、長寿命・省エネルギー性・瞬時点灯といった特性により、あらゆる分野で採用が進んでいます。さらに、調光・調色機能やIoT連携によるスマート制御など、照明設備はより高度なシステム化が進んでいる。
照明は、単なる「明るさの提供」にとどまらず、空間に機能性と快適性、さらには感性を加えるデザイン要素でもあります。適切な照明計画と設備選定は、安全・効率・美しさのすべてを両立させる鍵となる。